私はこのブログで、臨床医が行う研究の必要性について真面目に書いてきた(『臨床研究のすゝめ』『臨床医と研究者の違い』『臨床と研究の両立は必要か』参照)。この数年は、医師による研究を推奨するシンポジウムやワークショップに登壇し、講演する機会も少なくなかった。正直、研究をしている側からすると幾らでも大義名分はあるし、研究をする理由は見つけられる。一方で、研究には苦痛と犠牲を伴うことは否定できないし、研究をする全ての医師が惑わず研究に従事しているとは思わない。
「自身は世の中を変える研究ができているのか。そうでないとしたら、自分の研究に意味はあるのか」
「本質から外れた事務作業の多さと煩雑さ、臨床現場での研究のお邪魔感、応援よりも批判に近い査読コメント、自身の時間とお金の犠牲等、医学という社会の発展を望んで行う善意の研究がなぜこんなにも阻まれるのか」
今回は、研究に疲れた人、疑問を持っている人のために、いつもと違った立場で研究について考察してみる。
好きな人が研究すればよい
探究するのが好き
なぜ(研究に従事している)医師は研究しているのか。一言で言うと、研究が好きだからである。色々と大義名分や理由をを後付けすることはできるが、結局は好きで自発的にするものある。
研究とは、未知の真実を明らかにするために、体系的な方法で物事を深く調べ、探求することである。日々向かい合っている患者の病気に向き合っていると、様々な疑問が生まれる。より早期に発見する方法はないのか、この治療は本当に有効なのか、もっと良い治療はないのか。人間という生物や病気に関し、未知の真実を明らかにし、新しい知識を得るために探究心が芽生える。研究とは、ある対象に興味を持ち、内から湧き出る疑問を抑えきれず、答えを知ることで喜びを得るものである。
研究が自身の内から湧き出る疑問に対する探究的活動であるという点では、究極的には自己満足である。多くは真実を知りたいから調べているだけである。医師であっても探究心は人それぞれであり、物事を批判的に捉え、納得できなければ調べ尽くす医師もいるし、教科書や論文に書いてあることを素直に信じて実践する医師もいる。探究心のある者が探究に興味のない後者に「疑問を持ちなさい、研究をしなさい」と説いたところで、好きの押し付けである。好きな人はやれば良いし、逆に好きでないのならやらなくて良い。研究は自由な活動なのである。
自己研鑽が好き
一般的に、医師は研究を行うことが推奨されている。私自身、複数の場で医師による研究を推奨する立場で講演してきた。疑問に対する探究的活動という内から湧き出る欲求を短時間の講演で説いても響かないと思い、外的な要素から訴えてきた。例えば、研究を行うことによって専門性を高めることができる。あるトピックに関し、教科書や論文を読んで知識を得るのと、実際に自身で研究を行うのとでは、知識の深みが全く違う。専門性を高めるには、その分野の研究を行うべきだ、という論理である。また、研究を行うことで客観性も鍛えられる。年功序列の残る日本では、年齢を重ねポジションが上がるにつれ、周囲から批評される機会は驚くほど減っていく。そんな中、匿名で行われる査読は忖度なしに批評される。自身の論理や思考回路を客観的に眺めるチャンスとなるのだ。このような理由づけを元に、医師に対して研究を推奨してきた。
しかし、落ち着いて考えてみよう。このような理由づけは全て、医師としてのレベルアップしたいなら、という前提が存在する。すなわち、向上心があり臨床医としての高みを目指すことが好きな人にとっては、研究を行うことで理想の自分に近づくのだ。つまり、成長したいから好きで研究を行っているだけである。より専門性を高めることができる、より客観的な視点を持つことができる自分になりたいから、その手段として研究するのだ。
当然、このような自身の向上に魅力を持たない医師もいる。そのような医師に対し、「研究して上を目指しなさい」と諭すのは、昭和ならまだしも令和の時代にはそぐわない。「上」とは何ですか?あなたと私の価値観は違います、となる。そして、後述するように、臨床医としてのレベルが担保され、患者に迷惑をかけない限りは「研究して上を目指す」必要はない。患者の予後を悪化させないという前提の下、やはり研究は自由な活動なのである。
好きであること
好きというのは、特に継続する際に強い影響力を持つ。例えば、健康のために運動をする人はいるだろう。しかし、健康のためだけに本当に運動が嫌いな人が、運動を長期間継続することは難しい。年単位の運動を継続している人は、結局は運動自体が好き、筋トレで体型が変わるのが嬉しい、疲労感や達成感が快感、健康になっている感覚が好きだから、継続できるのである。
医療においても、夜遅くの患者対応、後輩の教育、学会の仕事など、好きでやっている医師は少なくない。時にそれらは自己犠牲を伴うものでもあるが、世のため人のためになることをしている自分が好きなのだ。たまたま好きな事が他人のため、社会のためになっているという点で、win-winであるだけのことである。責任感や義務感でやっているだけだと反論する人もいるかもしれないが、それもまた、責任感や義務感のある自分が好きなのだ。
研究も同じである。2-3年といった短期間であれば、嫌々であったり、強制されたりで研究をすることもあるかもしれない。大学院の間だけ好きでもない研究に従事した人はいるかもしれない。しかし、何年も継続的に研究に従事している人の殆どは、自身が好きでやっているだけであり、そこに義務はない。
研究しない臨床医はレベルは低いのか
では、研究に従事しない臨床医のレベルは低いのだろうか。探究心のない、向上心のない医師は悪なのであろうか。答えはNoである。特に、それが患者目線であれば尚更である。
現代医療が求める最低限の医療であれば、ガイドラインを遵守していればよい。ガイドラインさえ読まない医師はマズいが、今現在の推奨されている医療さえ知っていれば、患者が受ける医療の質は問題ない。患者にとってガイドラインが合格点である現代医療にとって、自己満足または向上心の現れである研究の必要性を説くことは、患者にとっては大きな問題ではない。
研究はゲームである
研究と査読
研究が論文となり雑誌に掲載されるには、その価値があるかどうかを判断する査読というプロセスが存在する。研究の原稿が雑誌に投稿された際、その雑誌の編集者(editor)が該当分野の専門家に査読を依頼し、査読者(reviewer)として論文を評価してもらうものである。査読の本来の目的は、研究プロセスの最終確認である。倫理的に問題のないプロトコルに基づいているか、データの改竄等の怪しい点はないか、妥当な解析が行われているか、科学的に妥当な論理で結論づけられているか、専門家による第三者の目で一つ一つ吟味されるものだ。
査読とは、一般的に批判的に吟味されるものである。基本的には研究者側からは査読者が誰かわからず、査読者は忖度なしに論文を批評することが可能である。研究者は自身の研究と論文に対して驚くほど否定的な意見をもらうことになる。査読側と研究者側が何度かやり取りをして、編集者と査読者が納得して初めて、その研究が論文として雑誌に掲載されるのだ。
査読はゲームである
冒頭で「研究はゲームである」とは言ったものの、それは誤解を招く表現である。ヒトを含む生物を対象とする研究では、過去の悲惨な人体実験(興味のある人は『タスキギー梅毒実験』と調べてみるとよい)を繰り返さないためにも、研究結果が科学的に偽りのないものであるためにも、様々な細かいルールを定め、研究者に遵守することを求めている。そのプロセスは確かに「ゲーム」とは程遠いものである。
一方、研究を世に出すプロセスの一つである査読は、ゲームと似ている。ゲームには様々な定義があるようであるが、「参加者が戦略や技術を駆使して、決められたルールに従って何らかの目的達成を目指す行為」であるとするならば、それはまさにゲームであると言える。
もちろん、査読の本来の目的は真実を探究した研究であることの担保である。しかし、実際はある程度の戦略や技術を要する。査読では、一回目で「reject(掲載拒否)」、すなわち「雑誌への掲載に値しない」とされることもあるが、それぞれの批評に対する言い訳の機会を与えられる(revision: 要修正)こともある。査読者も人間であり、査読コメントへの対応次第では「せっかく親切にコメントしてあげているのに」と感情的に「reject!」とする査読者もいる。コメントへ丁寧に対応していると、「まぁよく頑張ったほうかな」と「accept(受理)」の返事をもらうこともある。査読コメントへの理解を示し取り入れつつ自身の主張を行う術は「戦略や技術」が必要なのだ。査読コメントへの対応を時に「defence」と呼ぶことがあることからも、査読というプロセスが査読者のコメントを「攻撃」、研究者の戦略的主張を「防御」としているゲームであることを示している。
ルールが正しいとは限らない
査読はゲームであるため、ルールが存在する。それは、先述べた査読システムそのものである。まずは雑誌の編集者が読み、査読の価値があると判断すれば複数の査読者に査読を依頼する。選ばれた査読者は批判的に評価し、修正により掲載に値するレベルにまで改善すれば「accept」、そのプロセスのどこかで掲載に値しないと判断されれば「reject」となる。
ルールは必ずしも正しいと限らない。真実を探究する研究の科学的妥当性を担保するための査読システムであったとしても、そのルールが正解とは限らない。掲載の可否は限られた編集者で決定されるし、査読者も編集者が選んだ限られた人数で行われる。研究者として素晴らしい人が査読することもあれば、私のような人間が査読することもある。その領域において臨床医としては著名であっても研究者としての実績は乏しい人が査読することもある。査読者は他の査読者のコメントが読めるのだが、自身の査読と他の査読者の査読で全く批評ポイントが異なることも少なくない。
統計学では100回のうち95回は真実があるであろう範囲を95%信頼区間というが、一つの論文に対する査読者の人数は100人どころかたったの2-4人程度である。査読結果に真実があるのだとすると、限られた査読者と編集者で決定された査読結果が、真実を示す可能性は如何程のものであろうか。
更に、先に述べたようなその時々の査読者の感情や日常業務との兼ね合いで査読の質や方向性が決まってしまう可能性もある。多くの雑誌において、研究者からは査読者の情報は不明だが、査読者からは研究者の情報は可視化されているため、忖度の可能性も否定できない。つまり、決して現在の査読システムが正解とは限らない。
しかし、これはゲームなのである。自分が参加するゲームのルールに文句を言っても仕方がない。嫌ならやめたっていいのだ。ルールの範囲で楽しむのがゲームであり、考え方によっては査読もその一つである。
お金がかかる
研究にはお金が必要である。倫理委員会の審査、測定機器、検体検査、英文構成、雑誌投稿など、あらゆる研究プロセスでお金が必要となる。科研費や助成金といった研究補助金を獲得できる人は限られているし、研究にかかる費用を賄うには十分でないことも多い。また、殆どの医師は研究のための給料はもらっていない、すなわち研究に割く時間と金はボランティアである。世のため人のため、医学の発展のための研究であるはずなのに、なぜお金がもらえないのか、と考える人もいるかもしれない。
しかし、繰り返しになるが、研究は趣味であり、探究的活動または自己研鑽なのである。好きだから行う自由な活動なのだ。そして、ゲームであり、お金がかかるのだ。研究費獲得は賞金みたいなものである。趣味やゲームはお金を稼ぐものではなく、お金を投じるものである。そう考えると、研究でお金がもらえないことも不思議ではない。
それでも研究が必要な理由
医学の発展
これまで述べてきたように、研究は趣味であり、ゲームの側面があり、お金がかかるものである。好きでやるものであって、他人から強制されるものではない。しかし、研究が医学を発展させてきたことには異論はなく、医学を発展させる責任のある者は研究を行わなければならない。医学の発展に寄与する者、それは、専門性の高い医学分野で活躍している人たちである。彼らが研究をすることは、ある種の義務である。
ここでいう専門性の高い人とは、〇〇科、といった専門科ではなく、その専門科の中の専門分野である。呼吸器内科の中でも肺気腫、形成外科の中でも母斑、小児外科の中でも小児肝移植、麻酔科の中でも小児心臓麻酔など、専門分野の中の専門分野において、国レベルの第一線で活躍している医師である。
専門性の高い分野というのは、閉鎖的である。専門性が高いが故、専門外からの意見が届きにくい。専門家にしか知らない事が多く、専門家にのみ理解できる感覚的なものまで存在するため、専門家以外の人は意見をしにくく、専門家は専門外からの意見を聞き入れない。ガイドラインは専門家によって作成される。その専門家が研究を行わなければ、その分野の発展はない。どんなに研究を行うことが個々の自由だと言ったところで、専門分野で活躍している人間は、医学の発展のために研究をする義務がある。
フェイクに振り回される
研究は好きで行う趣味であり、強制されないものだいうことを盾に、全ての臨床医が研究をしなくなったらどうなるだろうか。憂うべきは、臨床医と研究者の間に壁ができ、臨床医は研究者の作成した研究結果やガイドラインに従うのみとなることであろう。
世に出る研究が常に科学的に正しいとは限らない。人や団体の利害や利権は様々であり、大きな金と命が左右される医療がその対象となることは容易に想像がつく。高血圧治療薬のディオバンに関わる論文不正事件(俗に言う『ディオバン事件』)が良い例であろう。もし臨床医が研究をしなくなったら、その研究結果やガイドラインが嘘であったとしても、臨床医はそれを見抜けない。なぜなら、研究をしない臨床医は本当の意味で研究を批判的に読むことができないからである。臨床医が誰も研究をしなくなったら、臨床医、そして患者が、政治と金に振り回される労働者であり被害者になるであろう。
臨床医が臨床医と患者を守るためには、誰かが研究をしなければならない。医学の発展と同様、臨床医の立場を守るという広い視点、大局的に捉えるのであれば、誰かは研究をしなければならない。
まとめ
例外はあれど、研究は強制ではなく自由な活動である。趣味でありゲームのような側面もある。お金を稼ぐものではなく支払うものである。そして、ルールは正しいとは限らない。研究に疲れた人は、自分を追い込み過ぎず、休んだら良い。好きでもないことを無理やりさせてもよい結果は生まれない。そして、やる気が出た時にまたやれば良いのだ。なぜなら、内から湧き出るモチベーションで研究が遂行されるのが理想だからである。

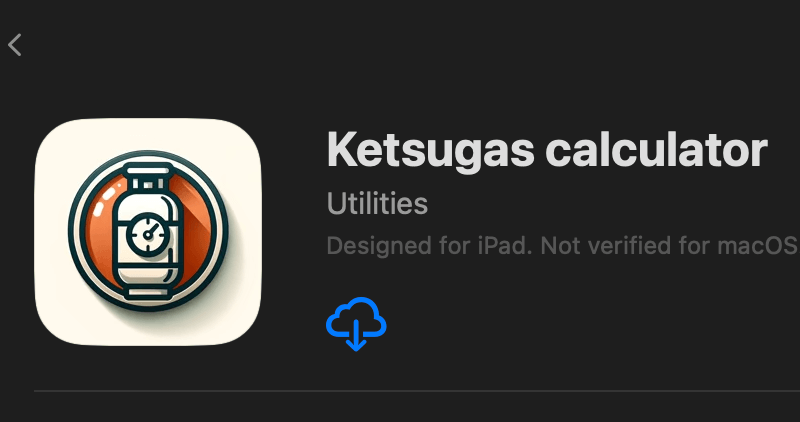
コメント